さまざまな業務に携わり、日々いろんな経験をしながら成長するのが新人看護師。
実際に働いてみると、患者さんだけでなく患者家族とのかかわり方で難しさを感じている人も多いのではないでしょうか。
この記事では患者家族とどのように接して良いのか分からない新人看護師に向けて、よくある事例やかかわり方のコツや、最適なコミュニケーション方法をご紹介します。
コミュニケーションスキルを磨いて、患者さんの家族に信頼される看護師を目指しましょう。
患者家族とのかかわり方【4事例】
患者さんに看護ケアを行う上で、患者の家族と話す機会が多くあります。
まだ仕事に慣れない新人看護師は、さまざまなタイプの患者家族と上手く接することができず悩むこともありますよね。
ここでは患者家族とのコミュニケーションや対処方法を事例を通じて学んでいきましょう。
家族から質問されたときの対応
病室やナースステーションなどで患者家族から質問されたとき、どのように返事をしていいのか分からず困ることがありませんか。
単純に自分の経験が浅く知識不足の場合だけでなく、薬・治療内容や入院手続きなど、自分の判断だけでは回答できない内容も多いでしょう。
すぐに回答しなきゃと焦って、憶測で伝えるとトラブルの原因になります。
とくに治療方針に関することは医師に確認をとる必要があるため、慎重に進めなければなりません。
まずは患者家族の疑問を丁寧にヒアリングして、どのようなことに不安があるのか把握しましょう。
「私からは今すぐにお応えすることができないので、今伺った点について医師(薬剤師・事務)に確認をとり、〇時までにお返事しますね。」
と出来ること・出来ないことをはっきりと伝えることが大切です。
患者家族は、病院の中で一番身近な看護師を頼って、不安や疑問を打ち明けてくれます。
他業種との架け橋として、患者家族の思いを聞き出すことに専念しましょう。
意識障害のある患者と家族への対応
脳血管疾患など急性期病棟やICUなどでは、意識レベルが下がり、話すことが出来ない状態の患者さんがいらっしゃいます。
患者家族は、元気な頃とは違って、点滴やモニターなどに繋がれている姿に大きく動揺し、どのように患者と関わればいいのか困惑していることも少なくありません。
新人のうちは看護業務をこなすことに精一杯になってしまいがちですが、患者さんの言葉を代弁するように声かけをしていくことで、患者家族の安心につながります。
「〇〇さん、ご家族がいらっしゃいましたよ」
「今日は表情が明るいですね」
と積極的に声かけを行いながら、患者家族が徐々に話しかけたり、清拭など身体に触れたりすることを促しましょう。
会話でのコミュニケーションだけでなく、視線や手足の動きなど非言語的コミュニケーションで患者と意思疎通が図れるということを患者家族に示すことが重要です。
訴えや要求の多い患者家族
家族が病気になり入院となると、悲しみ・怒りなどの負の感情がさまざまな形で表れます。
そのなかでも、患者に毎日かかわっている看護師に対して、さまざまな訴えや要求となって強い不安をぶつける場合も少なくありません。
「点滴の速度はこんなに遅くていいのか?」
「もっと吸引をしっかりしてほしい。」
など看護師の行動を細かく観察し、スタッフの名前を記録しているケースもあります。
医師の指示通りに適切に看護ケアを行っていることを一方的に伝えても、患者家族が納得していないと余計に不安を煽ることになりかねません。
まずは訴えの内容をよく聞いて、なぜそう思ったのか理由や経緯をくみ取りましょう。
何を言われるんだろうと患者家族を避けるように行動するのではなく、積極的に家族とコミュニケーションを図ることで、自然と話す機会が増えて信頼につながります。
病院の決まりに非協力的な家族
面会時間を過ぎているのになかなか帰ってくれない、病気で禁止されているのに食べ物の差し入れをこっそり持ってきているなど、看護師が対応に困ってしまう患者家族がいます。
病院の規則を守ってほしくて何度も説明しているのに、思うように理解が得られないと口調が強くなったり表情が固くなったりしていませんか。
と一方的に病院の決まりを守るよう押し付けるのではなく、患者家族を労ったり治療の経過をわかりやすく伝えたりすることも大切です。
など間接的なアプローチも入れて、患者家族の立場に寄り添いましょう。
かかわり方を少し変えると、なぜその行動をとっているのか理由が分かり解決策がみえてくることがあるからです。
患者家族とのかかわりで悩んだら転職して心機一転!
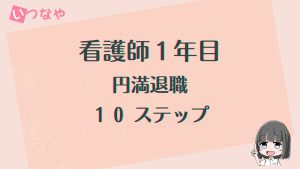
患者家族と良い関係を築く4つのポイント
患者家族と上手く接するためには普段の業務中から気を付けるべきポイントがいくつかあります。
患者さんやそのご家族とスムーズなコミュニケーションがとれるよう4つのポイントを把握して実践しましょう。
話をていねいに傾聴する
看護記録をとることに夢中になっていると、患者さんや家族と目線を合わせて会話ができていないことがあります。
安心して話せる雰囲気がないと、患者家族は医療者に遠慮して相談できなかったり、信用できないと思われたりすることにも繋がります。
患者家族と話すときは意識的に頷いたり、相手の言葉を繰り返すことで「ちゃんと聞いていますよ」ということを示しましょう。
話している最中にチラチラと時計を見たり電子カルテに記録しながら聞いたりするのではなく、相手のペースに合わせてゆったりとした気持ちでかかわることで患者家族の率直な思いを聞くことができます。
看護師からの説明も信頼して聞いてもらえるようになるので、信頼関係を構築する上でメリットが大きいでしょう。
挨拶をキチンとする
小刻みなスケジュールで慌ただしく病棟を駆け巡っていると、周囲からどう見られているか配慮することを忘れていませんか。
患者さんや家族は、直接かかわるとき以外の看護師の様子をよく観察していることが多いです。
患者家族とすれ違ったのに目配せだけで終わってしまうと、自分は会釈して挨拶したつもりでも「無視された」
と思われているかもしれません。
病棟では「こんにちは」と一言でも挨拶があると印象がガラッと変わり、話しかけやすい看護師と認識してもらえます。
また、治療や看護ケアをご家族に説明する際にも、注意が必要です。
難しい言葉を使わず相手の反応をみながら話すことや、面会時間以外の患者さんの様子を一言添えることを意識してみましょう。
家族背景を理解する
キーパーソンと良好な関係を持つことや家族背景を十分に理解してかかわることは、患者の治療やケアを円滑に進める上で重要です。
患者さんによっては、キーパーソンとその他の家族で意見が分かれて、治療方針の同意・説明を複数回行ったりトラブルに発展したりする恐れがあります。
まずは基本的な家族構成や、家族の仕事・疾患の有無についても把握しましょう。
その他にも、患者以外に介護が必要なご家族がいたり問題を抱えたりしていないか、入院時の情報収集をしっかりと行うことが大切です。
家族の精神的・体力的負担を理解して、看護師に相談できるような関係づくりを目指しましょう。
家族や患者目線で環境を整える
入院中の患者さんのベッド周辺や病室などの環境整備は看護の基本です。
清潔で安全に保たれた病室は、患者さんの心身の健康促進だけでなくご家族の安心にもつながります。
便利だからとベッド周辺に医療テープやガーゼを置きっぱなしにしたり、血液などで汚染された白衣やナースシューズで患者さんに接してはいませんか。
また、汚れたリネンや病衣をすぐに交換せず、後回しにするのも好ましくありません。
患者が過ごす病室の評価は、看護師の信頼度に影響します。
患者とその家族と良好な関係を築くためにも、心地よい生活環境づくりに日々取り組みましょう。
患者家族の立場を理解して寄り添う
患者さんとその家族との良好なコミュニケーションには、看護師が意識的に話しかけやすい雰囲気を作ったり、患者家族の立場を理解して寄り添うことが大切です。
自分の家族が入院していたら、どのようにしてほしいか考えることで、良いかかわり方が見つかるかもしれませんね。
患者やその家族に求められることはさまざまですが、柔軟に応えられるような看護師を目指して頑張りましょう。
