病院やクリニックで勤務していると、さまざまな患者さんに出会います。
看護師として働いていれば、患者さんとコミュニケーションをとる中で、「ありがとう」と直接感謝されることも多いでしょう。
一方で、患者さんから、対応に困ったクレームを言われることも少なくありません。
この記事では、患者のクレームの事例とその対策、クレームにつながらないために看護師がすべきことをご紹介します。
患者さんとの上手な向き合い方を学んで、看護師としてのスキルを磨きましょう。
患者の理不尽なクレームとその対応策
入院中や通院など、普段の生活と異なる状況下では、患者のストレスや不満は大きくなります。
ここでは、看護師がよく遭遇する患者からのクレームと、その際の患者への接し方をご紹介します。
患者の理不尽なクレーム「他の看護師を呼べ!」
看護師として経験が浅いと、採血や点滴・注射などで失敗してしまうこともあるでしょう。
「練習しないと上手にならないよ!」
と新人看護師に付き合ってくれる親切な患者さんも稀にいますが、一度失敗すると
「できないなら他の看護師を呼べ!」
と厳しい言葉をかけられることもあります。
なかには見慣れたベテラン看護師しか信用してもらえず、顔なじみのない看護師だと言うことを聞いてもらえなかったり、生活援助の際も嫌な顔をされたりといった経験をした人もいるかもしれません。
痛みや緊張感をともなう手技は、相手を不安にさせることなくスムーズに終わらせるのがベストです。
何度も失敗してしまうと苦痛を与えてしまうので、クレームを言われた場合はすぐにお詫びして他の看護師を呼びましょう。
このような患者さんは看護師の行動を細かく観察しています。
ベテラン看護師の物品の置き方や、声かけ、テープの貼り方など細かいところを真似すると、患者さんも安心してくれるでしょう。
患者の理不尽なクレーム「外出許可を出してくれ!」
入院中の患者さんのなかには、病院のルールを守れなかったり医師からの指示を聞いてくれなかったりということから、クレームやトラブルに発展するケースが多くあります。
とくに病状が安定してくると勝手に外出しようと荷物をまとめて、病院から出てしまう患者さんもいるため対応には注意が必要です。
認知症や精神疾患をもっている患者さんは、病識がないため、外出できないことをなかなか理解してもらえません。
そのため病院に閉じ込められているという思いが強くなり
「もう元気なんだから外出させてくれ!」
と訴えます。
病識があっても「タバコを吸いたい」「お酒を飲みたい」といった欲求が勝り、無断で外出してしまう困ったケースも少なくありません。
このような患者さんには、医師から改めて外出について説明してもらったあとに、患者の気持ちをくみ取りながら、外出できない理由と無断外出した場合のリスクを看護師からも説明しましょう。
患者の理不尽なクレーム「予定があるから早く検査して!」
検査や手術など、予定時間より遅れてしまうと
「このあとに予定があるから早めてもらえないか?なぜ時間通りでないのか?」
といったクレームをいただくことがあります。
救急対応のある病院では緊急手術などで当日に予定が変更することも多く、予定されていた患者さんを長時間待たせてしまうことも少なくありません。
優先度によって時間が遅れることに対して事前に説明があっても、自分がないがしろにされた気持ちになり、怒りや不満をぶつけてくる患者さんもいるでしょう。
このような患者さんには、待たせてしまっていることを詫びて、時間になるギリギリまで自由に過ごせる環境を整えます。
「申し訳ないのですが、他のみなさんも同じように待っている状況です」
ということをしっかりと伝えて特別扱いできないことを理解してもらいましょう。
患者家族の理不尽なクレーム「話が違う!」
看護師が経験するクレームには、患者だけでなく患者の家族からのケースもよくあります。
「薬や治療内容が聞いていた内容と違う」
「病状が良くならないが、本当に大丈夫なのか?」
といった、治療に対する不信感を看護師に漏らすご家族もいらっしゃいます。
患者さんに行う治療は必ず事前に説明・同意を得ますが、医師からの説明が分かりにくかったり勘違いしていたりと食い違うケースがあるため、看護師からも不明点はなかったかきちんと確認することが重要でしょう。
患者さんの病状によっては安全のために身体拘束をする場合があります。
本人・家族から同意を得たとしても
「ここまでしないといけないのか?」
と疑問を持たれることもあるため
「どんなリスクがあるのか」
「どのように看護ケアをしているのか」
を実際に見てもらいながら不安を払拭することが求められます。
クレームに心折れたら心機一転!
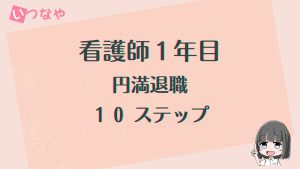
患者の理不尽なクレームを未然に防ぐための対応
病院やクリニックでのクレームは、ある程度予測がつくことがあります。
患者さんにとって身近な存在である看護師が、患者さんの立場になって行動することを意識すれば、未然に防ぐことも可能となるでしょう。
ここではクレームを防ぐためのポイントを解説します。
相手の気持ちに寄り添う
患者さんからのクレームは、看護師や病院スタッフの態度・言動の一つ一つが積み重なって引き起こされることがあります。
治療や検査などで難しい言葉を使って早口で話しても、患者さんに伝わっていなければ説明したとは言えません。
また看護師が業務をこなすのに必死になると、患者さんも急かされていると感じたり待たせているのに要件だけ伝えて、相手を労うことを忘れてしまったりと失礼な態度をとっているかもしれません。
こうした対応は患者さんに疑問や不安を増大させる要因となり
「対応が悪い!どうなっているんだ」
というクレームにつながりやすくなります。
まずは相手に合わせた言葉選びや
「お待たせして申し訳ありませんが~」
「恐れ入りますが~」
などといった丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
可能な範囲で希望に応じる
病棟や外来では患者さんに応じた臨機応変な対応が求められます。
たとえば血が苦手な患者さんに対しては、希望に合わせて安全に採血をするために、初めから寝た姿勢で実施することが多いでしょう。
患者さんが心を開く看護師や医師が限られていると、決められた看護師が担当することもまれにあります。
このような対応は業務全体に支障が出ない場合には行うことができますが、全ての要望に応えて患者さんを特別扱いすることは難しいです。
しかし少しでも快適に過ごせるように患者さんがどのように感じているのかを考慮することで、満足度が向上し、トラブルを防げるでしょう。
患者の要望や特徴は迅速に情報共有する
カルテには患者さんの疾患や治療経過だけでなく、患者さんの職業や細かな言動・様子も記録されています。
とくにクレームに発展しそうな場合は、どのような状況でどんな発言をしたのかを情報共有することでスタッフの対応を統一できます。
また外来の場においても、怒っている人や神経質な人などは特に配慮しながら対応しなければなりません。
受付や待合室、診察室など複数のスタッフが連携して円滑に業務が進むように、患者さんの要望や質問内容を共有することが大切です。
クレームやトラブルが発生した時に看護師ができること
患者さんからのクレームやトラブルが起きた際には、事態を大きくさせないためにもクレームを聞いた看護師の行動が重要となります。
患者さんにどう対応すべきなのか4点に分けて解説します。
冷静な態度で相手の話を聞く
患者さんが大きな声で怒っていると、初めてクレームに対応する看護師は少なからず動揺してしまいます。
無理な要望にもどうにか応えないといけないと感じたり、事実と異なることを言われて反論したくなったりもするでしょう。
しかし、まずは相手の怒りの原因を知るためにも、冷静になって話を聞く姿勢が大切です。
患者さんが言いたいことを全て聞くまでは、途中でさえぎってはいけません。
また、困った顔やイライラした顔など感情は出さず、きちんと聞いていることが相手に伝わるように気をつけましょう。
不快な思いをさせたことに対して詫びる
患者さんからのクレームには毅然とした態度で接することが重要ですが、まずは不快な思いをさせてしまったことを謝罪しましょう。
クレームの内容が事実と異なる場合や、かかわった看護師に非が無いこともありますが、途中で反論してしまうと事態を悪化させてしまうリスクも少なくありません。
クレームをいう患者さんは、話を聞いてほしいという思いが強く、精神的に不安定になっていることが要因の場合があります。
まずは落ち着いた環境を整えてクレーム内容をきちんと受け止めていることを示しましょう。
他の看護師・医師を呼ぶ
1人での対応が困難だと判断したら、すぐに他の看護師や医師を呼び、複数で対応することが大切です。
1人だと精神的な負担だけでなく、その場しのぎの約束をしてしまうなど誤った対応をとる危険があるからです。
今後の再発防止策を講じるためにも、客観的な視点で記録をする人や、相手が納得できるように交代して説明をする人も必要でしょう。
複数人で対応することで暴力行為に発展することを予防し、相手を落ち着かせることができます。
まとめ
患者さんからのクレームはさまざまで慣れないうちは対応が大変ですが、そこから看護師として学ぶことも多くあります。
患者さんの立場になって考えながら、適切なコミュニケーションをとってクレームに対応していきましょう。

