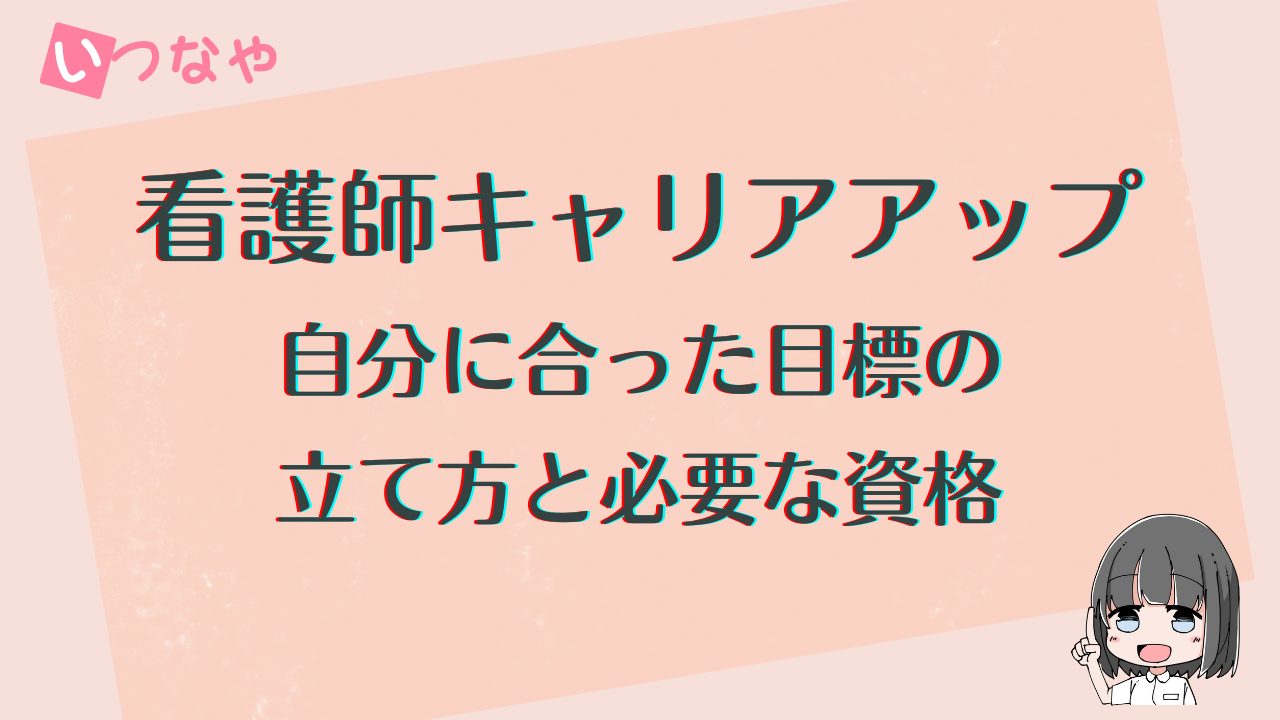看護師として経験を重ねるうちに、「看護師としてどのように働きたいか」と、今後のキャリアについて考える方もいるのではないでしょうか。
目指す方向性によっては取得しておきたい資格も異なり、それぞれ事前準備が必要です。
この記事では、看護師キャリアアップの方向性や取得できる資格、資格の概要について解説します。
今後、看護師として働くならキャリアアップを考えておくことが大切です。
ぜひ本記事を読んでキャリアプランの選択にご活用ください。
看護師キャリアアップの方向性
看護師キャリアアップの方向性は、大きく以下の2つに分けられます。
スペシャリスト看護師
ジェネラリスト看護師
それぞれどのような特徴や取得できる資格があるのか、みていきましょう。
スペシャリスト看護師
スペシャリスト看護師とは、特定の専門分野において知識や技術を有している看護師のことです。
代表的な資格として、日本看護協会が定めている「専門看護師」や「認定看護師」などがあります。
豊富な知識とハイレベルな看護技術により、より質の高い看護を提供するのが目的です。
もちろん、対象は患者個人に限りません。
ほかの看護師の指導やマネジメント、看護業界全体のスキルの向上などといった分野にも貢献することが求められています。
そのため以下のような人は、スペシャリスト看護師に向いていると考えられます。
- 専門分野を極めたい
- もっとスキルを深めたい分野がある
- 特定分野の人材育成や研究にも興味がある
ジェネラリスト看護師
ジェネラリスト看護師とは、特定の分野にこだわらず臨機応変に患者のニーズに応え、その場に即した看護を提供できる者のことです。
診療科にとらわれず、幅広い技術と高い技術が求められます。
日本看護協会では、「経験と継続教育によって習得した暗黙知に基づき、その場に応じた知識・技術・能力が発揮できる者」と定義付けられています。
スペシャリスト看護師と異なり、これといった資格などはなく、抽象的な印象があるかもしれません。
病院によってクリニカルラダーなどを設定しているケースもありますが、能力が見えにくいという特徴があります。
しかし、ジェネラリスト看護師は医療施設を始め、在宅医療や看護師の常駐人数が少ない地域施設などでは欠かせない能力となるでしょう。
ジェネラリスト看護師に向いている人は、以下のような傾向にあります。
- さまざまな診療科を経験したい
- 病院以外の現場でも経験を積みたい
では、スペシャリスト看護師とジェネラリスト看護師の道を選んだその先は、どのような資格を持つべきなのでしょうか?
看護師キャリアップのためにとるべき資格
資格を取得すれば、ある分野において体系的な知識と技術を身に付けているというアピールになります。
客観的なスキルの証明になるのです。
将来、転職や復職、管理職へのキャリアアップにも有利に働くでしょう。
ここでは看護師のキャリアアップに役立つ資格を解説していきます。
専門看護師
専門看護師は日本看護協会が定める資格です。
特定分野の知識や技術を有していると専門看護師制度委員会により認められた証です。
特定されている分野は以下の14分野です。
これらの専門分野で求められる役割は、以下の6つです。
- 実践:患者や家族に対して、質の高い看護を提供する
- 相談:コンサルテーションを行う
- 調整:保健医療福祉に携わる人々のコーディネートを行う
- 倫理調整:倫理的問題の解決を図る
- 教育:教育的役割を果たす
- 研究:専門知識や技術の向上のために研究活動を行う
ニーズを総合的に捉える力と広い視野を持って、施設全体や地域の看護の向上に努めます。
専門看護師の資格取得を目指す場合、以下の要件を満たす必要があります。
実務経験が通算5年以上、うち3年以上は専門看護分野の実務がある・看護系大学院修士課程修了者で日本看護系大学協議会が定める専門看護師教育課程基準の所定の単位(26単位または38単位)を満たしていること
修士課程を修了していることが前提であるため、大学院に進学していない場合は2年間大学院に通わなければなりません。
もちろん、大学院に入学するための試験対策も必要です。
要件を満たせば、認定審査を通過したのちに認定証が交付されます。
 まな
まな5年ごとの資格の更新も必要になります。
専門看護師になるためには、上記のように長い時間かかります。
資格取得のために、大学院の費用も含めて約200万円ほどかかるとも言われています。
その場合、日本看護協会が設けている支援金制度や医療法人が独自に設けている奨学金制度の利用がおすすめです。
自身が勤務する医療法人に該当する制度がないか確認してみましょう。
認定看護師
専門看護師として混同されやすい認定看護師ですが、こちらも専門看護師と同じく日本看護協会が認定する資格です。
専門分野の知識や技術に長けており、質の高い看護を提供する点においては両者とも変わりありません。
しかし特定分野が異なり、認定看護師のほうがより限定的になっています。
以下が認定看護師の特定分野の一覧です。
求められる役割も異なります。
日本看護協会が求める認定看護師の役割は以下の3つです。
- 実践:患者や家族に対して、質の高い看護を提供する
- 指導:看護職に対して指導を行う
- 相談:コンサルテーションを行う
専門看護師の場合、以下の3つも加わるため、認定看護師のほうが求められる役割は少ないということになります。
- 調整:保健医療福祉に携わる人々のコーディネートを行う
- 倫理調整:倫理的問題の解決を図る
- 研究:専門知識や技術の向上のために研究活動を行う
認定看護師の資格取得を目指す場合、以下の要件を満たす必要があります。
実務経験が通算5年以上、うち3年以上は認定看護分野の実務があること・認定看護師教育機関で教育課程を修了すること
教育課程に必要な時間は分野ごとに異なりますが、おおむね800時間前後、6〜8カ月ほどかかります。
要件を満たした後、認定看護師認定審査に通れば、認定証が交付されます。



こちらも書類審査にて5年ごとの資格更新が必要です。
資格取得のしやすさから言えば、大学院に2年間通わなければならない専門看護師よりも認定看護師のほうが取得しやすいと言えるでしょう。
2022年での登録者数は、専門看護師2,900名に対して、認定看護師が22,500名となっています。
これらの数字からも専門看護師よりも認定看護師のほうが取得へのハードルが低いと伺えます。
とはいえ、認定看護師の資格を取得するにも種々の費用が必要になります。
認定看護師の新たなカリキュラムに特定行為研修が追加され、約30万〜100万円程度かかる見込みです。
そのため資格取得を目指す場合は、日本看護協会の認定看護師教育課程奨学金や各種支援金、奨学金などを利用するのも1つの方法です。
認定看護管理者
認定看護管理者とは、病院や施設の管理者として質の高い看護を施設全体で提供できるよう、体制を整えられる看護師のことです。
日本看護協会が認定しています。
ベッドコントロールや人員調整など、スタッフを束ねて病床を効率的に回すには、これまでと異なるスキルが求められます。
そのため今後管理職として看護師長や看護部長、主任などを考えている場合は、取得しておきたい資格の1つでしょう。
資格取得のための要件が以下です。
実務経験が通算5年以上、うち3年以上は看護師長相当以上の看護管理の経験があること・認定看護管理者教育課程サードレベルを修了していること・看護管理に関連する学問領域の修士以上の学位を取得していること
認定看護管理者の教育課程は、ファーストレベル・セカンドレベル・サードレベルに分類されており、それぞれ受講要件や必要な時間数が異なります。
ファーストレベルを修了してからセカンドレベルへ、セカンドレベルを修了してからサードレベルへ、というように段階的に進めていくカリキュラムになっています。
それぞれ要件を満たした後、日本看護協会による審査があり、通過すれば認定証が交付されます。
こちらも5年ごとの更新が必要です。
保健師
保健師は、保健師助産師看護師法にて「厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とした者」とされる国家資格です。
主な業務は以下のようになっています。
- 健康診断:乳幼児健診、職員健康診断など
- 相談業務:育児相談、虐待、生活習慣病、感染症対策、メンタルヘルスケアなど
- ストレスチェック
- 健康教室の開催
- 地域に向けた健康教育・指導・啓蒙活動
また保健師が活躍できる場も多岐に渡ります。
- 行政保健:保健所、保健センター
- 産業保健:一般企業
- 学校保健:学校、大学など
- 病院保健師:病院、クリニックなど
保健師資格を取得するには、1年制の保健師養成学校に進学し、保健師国家試験に合格する方法があります。
保健師国家試験の合格率は過去80%〜100%近くで推移していますが、既卒者のみの合格率は令和3年度で53%です。
行政看護師として働く場合は、公務員試験にも通らなければなりません。
助産師
助産師は、保健師助産師看護師法にて「助産又は妊婦、じょく婦もしくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」と定められている国家資格です。
助産師は看護職のなかで唯一分娩を進められる権限を持っています。
正常分娩に限り、医師の指示がなくても助産行為を進められるのです。
以下が助産師が担う業務の一部です。
- 出産介助(正常分娩に限る)
- 新生児の観察
- 授乳指導
- 乳房マッサージ
- 保健指導
- 母子手帳など出産に関する書類の記入
そのほか、ハイリスク妊婦の全身管理や死産・中絶の処置、心理的ケア、若年層の性教育などの役割を持ちます。
助産師になるには、1〜2年制の助産養成施設への進学が定められています。
国家試験を受けるには、助産にまつわる科目の単位数を履修しなければなりません。
助産学実習を修了するためには、おおよそ10回程度の分娩介助が必要です。
そのため、夜間や休日中の呼び出しや、いつ分娩が始まるかわからない緊張感などの大変さがあるでしょう。
試験に合格し、厚生労働大臣より免許を交付された後は病院や診療所で勤務される方が全体の8割以上です。
試験の合格率は例年99%以上であり、令和3年は既卒者11人中9名が合格しています。
決して難易度の高い試験ではありません。
特定行為看護師
特定行為看護師とは、特定行為として定められている38種類の行為を、医師の指示を待たずに行える看護師のことを指します。
特定行為看護師がいれば、医師がすぐに指示を出せない状況でも、自らの判断で患者に適した処置を行えます。
タイムリーに患者に処置を行うことで、患者の症状の回復や苦痛の軽減を早期に図れるのです。
今後、医師が常駐していない在宅医療や施設などでの活躍が期待できる資格でしょう。
以下は、特定行為として定められている内容の一部です。
- 侵襲的陽圧換気の設定変更
- 気管カニューレの交換
- 一時ペースメーカーの操作及び管理
- 心のうドレーンの抜去
- 橈骨動脈ラインの確保
- インスリン投与量の調整
どの行為も高度なスキルと判断力、専門知識が必要になります。
特定行為看護師になるためには、特定行為研修を受講しなければなりません。
特定行為ごとに研修が設けられており、受講場所やかかる期間、費用なども異なります。
全研修はおおむね3年〜5年の実務経験が必要ですが、詳細は日本看護協会の「看護師の特定行為研修制度」にて確認できます。
ケアマネージャー
ケアマネージャーは介護支援専門員とも呼ばれ、高齢者と介護福祉サービスのマネジメントを担う職種です。
介護を必要としている人にどのようなサービスが利用できるか、利用者のヒアリングのもとケアプラン作成やサービス事業者との調整を行います。
主な業務内容は以下になります。
- 介護相談
- 介護認定の書類作成
- ケアプランの作成
- モニタリング
そのほか、生活保護申請の補助や配食サービスの調整など業務内容は介護業務のみに収まりません。
ケアマネジャーになるためには介護支援専門員実務研修受講試験の合格が必要です。
受験条件として一定の業務経験が通算5年以上かつ従事した日数が900日以上であることが求められます。
一定の業務には看護師、保健師、助産師も含まれます。
試験の合格率は例年10%〜20%と、難易度の高い試験と伺えるでしょう。
ただこれまで紹介した資格とは異なり、独学や通信講座を利用して資格取得を目指せます。
仕事と両立しながら学べるので、金銭面や時間などに制限がある方にはおすすめです。
学会認定看護師
特定分野の各学会から認定を受け、深い知識と高度なスキルを持つと認められる資格です。
学会認定看護師は以下のような種類があります。
- 自己血輸血看護師
- 臨床輸血看護師
- 運動器看護師
- HIV感染症看護師
- HIV感染指導看護師
それぞれ学会が設けた試験に合格しなければなりません。
受験資格は学会ごとに異なりますが、おおむね各学会の会員であること、実務経験が3年〜5年以上あることなどが求められます。
受験資格の詳細は、各学会の公式ホームページに掲載されています。
そのほかの資格
そのほか、看護師におすすめの資格です。
- 臨床心理士
- 社会福祉士
- BLS・ACLS・PALSプロバイダー
- 消化器内視鏡技師
- 認知症ケア専門士
- 呼吸ケア指導士
- 周術期管理チーム看護師
- 皮膚疾患ケア看護師
- 新生児蘇生法インストラクター



自分のこれまでの経験や強みに合わせて、今後活用できそうな資格や必要なスキルをみつけてみましょう。
看護師キャリアアップのために必要な条件
看護師のキャリアアップには常に目標を持って、継続的に学びを深めていく姿勢が欠かせません。
そのためには自身のライフプランの構築やワークライフバランスがとれた職場の協力体制が必要です。
ここでは、看護師がキャリアアップしていくための必要な条件について解説します。
明確な目標と達成プラン
どの資格を取得するにせよ、自身が今後どのようなフィールドにいたいのか明確にすることが必要です。
専門性を極めたいのか、ジャンルにこだわらずに働きたいのか、管理職などを目指したいのか、などによって取得するべき資格が見えてくるからです。
資格によっては、一定の勤続年数や大学院卒業の学歴などが必要なものもあり、事前準備が必要になります。
目標や資格取得を達成するにはどのような事前準備が必要なのか、逆算して達成プランを打ち出してみましょう。
モチベーション
看護師のキャリアアップにはモチベーションが欠かせません。
資格を取る、スキルを身に付けるという意欲も、原動力になるものがないと継続しません。
原動力は人によってさまざまです。
- もっと患者の役に立ちたい
- 周囲から頼られたい
- 転職を有利に進めたい
- 報酬を上げたい
自身のキャリアアップのためにポジティブな原動力を持ち、モチベーションを高めていきましょう。
職場の協力体制
取得したスキルや資格をどう活かして活動できるかは、職場の協力体制にも左右されます。
- 職場との認識が異なり理解を得られない
- 職場の体制が整っていない
せっかく努力して取得した資格を効果的に利用できないケースも往々にしてあります。
まずは職場の上司と共通認識を持てるよう、事前に擦り合わせしておくことをおすすめします。
現在休職中や転職予定の場合は、採用試験の面接の際に今後取得予定の資格を伝えておくのもいいでしょう。
自分にあったキャリアアップを目指そう
看護師のキャリアアップで最初に考えることは、スペシャリストかジェネラリストかという視点です。
専門に特化した看護を深めたい場合は、5年以上実務経験があれば、専門看護師や認定看護師がおすすめです。
看護師が取得する資格の中でも、一番メジャーでもあり評価を受けやすいからです。
一方でジェネラリストとして幅広く活躍したいという場合でも、各分野で質の高い看護を提供できる資格や制度が整っています。
ジェネラリストを定義付ける資格はないものの、これらの資格や制度を利用して知見を深めるのもいいでしょう。
まずは自分が今後どのような働き方をしたいのか、ワークライフバランスも取り入れながら考えてみましょう。
助成金や支援制度も活用してみてください。